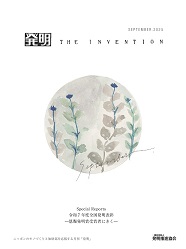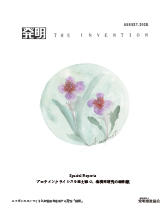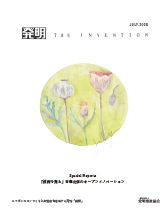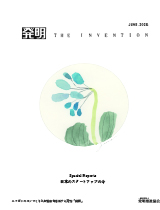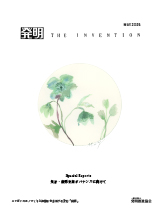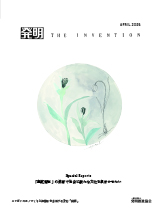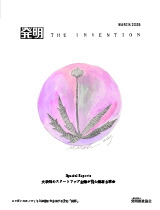�@ |
|
 |
�@�������́A����38�N�i1905�N�j�n���́u�H�Ə��L���G���v��O�g�Ƃ��A100�N�ȏ�̗��j���o�č����Ɏ����Ă��܂��B �@�����A���p�V�āA�ӏ��A���W�݂̂Ȃ炸���쌠�A�s�������h�~�@���A�m�I���Y���S�ʂɘj�����ԗ����A�V�N�ȏ��������������Ă���܂��B �@�����̏���y�ђm�I���Y�����x�̌[�ցE���y�̌������Ƃ��Ĕ�������y�є������i����̉���͂��Ƃ��A��ƌo�c�ҁA�����Ɩ��S���ҁA�Z�p�J���ҁA�ٗ��m�A�w�����A���L���ǎґw�ɂ��x���̂��ƁA���s���Ă���܂��B �@����WEB�łł́A�G���Ōf�ڂ��ꂽ�L�������J���Ă܂���܂��B �i���q�ł̒���w�ǁE�o�b�N�i���o�[�̊m�F���@�ɂ����j 2026�N1����
2025�N12����
2025�N11����
2025�N10����
2025�N9����
2025�N8����
2025�N7����
2025�N6����
2025�N5����
2025�N4����
2025�N3����
2025�N2����
�G���u�����vWEB�ł̉{���ɂ́AFlashPlayer9�ȏオ�C���X�g�[������Ă���K�v������܂��B�܂�Javascript��L���ɂ���K�v������܂��B FlashPlayer�́A�ȉ��̃T�C�g�ɂă_�E�����[�h�����������Ƃ��\�ł��B�i�����j �_�E�����[�h�T�C�g |
|||||||||||||||||||||||||